色彩文様研究所
石畳文・市松文
石畳文・市松文
御利益災難厄除 必勝祈願
市松文 とは、一般的に色の違う正方形を上下左右に交互に敷き詰めた格子状の文様を指す。この名称は、江戸時代中期の上方歌舞伎役者佐野川市松(いちまつ)が舞台衣装の袴(はかま)に愛用していた文様を、同時代の女性がこぞって小袖に取り入れたことから広まったといわれる。
市松登場以前は、石を敷き詰めた形に似ていることから、石畳文と呼ばれていた。この石畳文には、正方形を四十五度傾けてつなぎ合わせた文様や、二重の入れ子状に重ねた文様もある。とくにこの入れ子状の石畳文は、色絵磁器である古九谷(こくたに)様式の鉢や皿に多くみることができる。さらに時代を遡ると、平安時代には「霰(あられ)」という名称で、有職文様(ゆうそくもんよう)として公家の装束や調度品に用いられていた。このように市松文は、時代によって呼び方が異なってはいるが、文様自体は非常に古くから存在し、さまざまな工芸品に用いられていたことがわかる。[1]
色違い の正方形を交互に敷き詰めた入替文様。平安時代には「霰(あられ)」と呼んで地文にした。単純な構成文様なので古くから見られ、工芸品、染織品の他、桂離宮の襖のような室内装飾にも使われた。江戸時代の歌舞伎役者、佐野川市松が愛用したので俗に市松文様と呼ばれるようになった。[2]
白 と黒などのように、二種類の色の方形を上下左右が互い違いになるように並べた、碁盤目の文様。有職では「霰(あられ)」と呼びならわされているが、特にこの形の小紋を「霰」または「小石畳」と言って区別することがある。
江戸時代の元禄(1688〜1704)頃に流行した時は「敷瓦」と呼ばれ、江戸中期の歌舞伎役者、初世佐野川市松(1722〜62)が舞台衣装の裃(かみしも)に用いて流行して以来、広く「市松模様」と呼ばれるようになった。[3]
正方形 の板石を正しく敷きつめたものを石畳といい、古くは甃の字を用い、しきいし・しきがわら・いしだたみと読んだ。甃の形は必然的に考え出される形体構成で、古代から文様として種々なるものに表現された。この工芸的遺品として正倉院に「甃文雑色織裂」がある。経・緯とも太い撚り糸を赤と黄に染めたものを用いて甃文を桟崩(さんくず)し調に織りあらわした平組織の裂である。単純な技法によるものではあるが、院蔵中の特殊な織物の一つに数えられる。石畳文は平安時代に入っては束帯を着けた時に穿く表袴(うわばかま)の3位以上の高官の文様とされ、窠文を配して爾来江戸時代まで踏襲された。桃山時代から江戸初期にあらわれた名物裂の「遠州緞子」と呼ぶものは石畳を地文として、それに牡丹文か七宝文をあしらっている。江戸時代の歌舞伎役者の佐野川市松がこの文様を愛用したことから俗間に市松文様と呼ばれ、ついにその名の起りも知らずに石畳を市松と呼んで今日に至った。奈良時代の絁(あしぎぬ)地甃文裂」は布を正しく四角に折りたたんで、その上下の両側に板を当てて固く締め、その当て板より四方にはみ出た部分を染めた、いわゆる纐纈(こうけち)で、素朴ながら美しい甃文である。後には石畳を地文とし単花文・竹文・家紋などを散点状に配して染め出し、時に刺繍をも加えて小袖その他がつくられた。
◆ 市松
白と黒、という風に濃淡の異なる同じ大きさの正方形を一つ置きに配して構成した文様である。もと霰地(あられじ)から起って甃(いしだたみ)文と称し、石畳とも書いた。江戸時代に団七なるものの衣裳文様にされたことから「団七」と呼び、また徳川八代吉宗の時代に江戸中村座の役者佐野川市松が袴の文様に使って人気を博したことから「市松文様」といい、ついには石畳と呼ぶよりははるかに広く用いられるようになった。明治中期には、この文様が元禄時代に大流行したことから「元禄文様」と呼ぶようになった。古代から現代に到るまで甚だしい衰退もなく織物・染物・漆器・陶器・室内装飾・造庭など各種の方面に用いられている。[4]
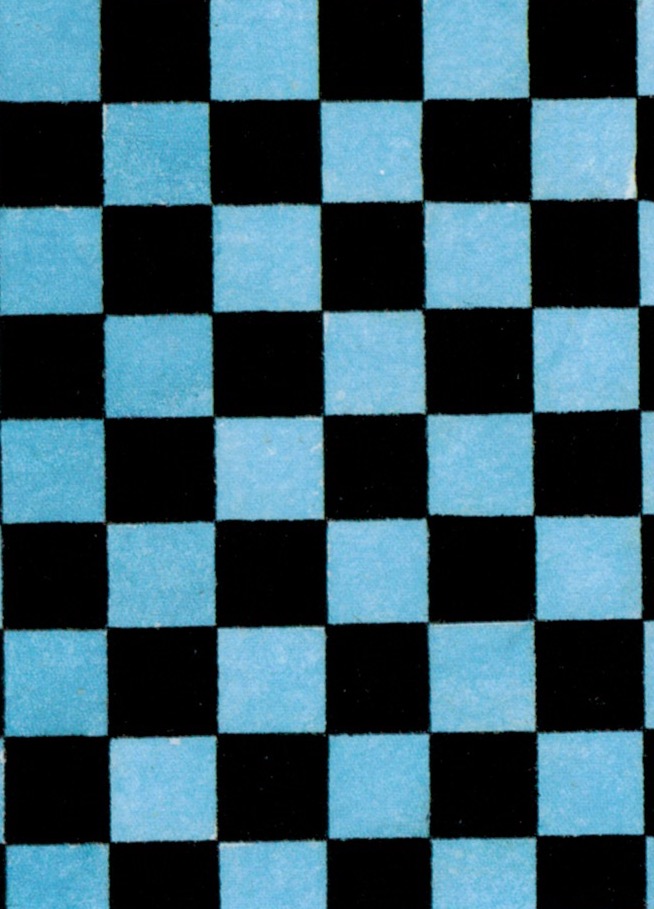

石川県立美術館蔵

文献等の用例
- たまきはる「こうばいのにほひのうはぎ、もん、いしだたみ」(1219)
- 日葡辞書「Ixidatami(イシダタミ)<訳>絹布、むしろ、ござなどに見られる(モザイクタイルを模倣した)格子縞模様の縞目とか刺繍」(1603)
- 浮世草子・好色二代男 – 八・二「拾八人揃帷子に<略>石畳(イシタタミ)の巾広帯、黒羽織夢という字の大紋」(1684)
- 談義本・八景聞取法問 – 二・棧敷の混乱「近年甃の模様をば市(イチ)松染と名を付て猫も杓子(しゃくし)も着て歩行(ありく)が」(1754)
- 蓼食ふ虫<谷崎潤一郎>一〇「宿の浴衣に市松の伊達巻姿で鏡の前にすわりながら」(1929)
